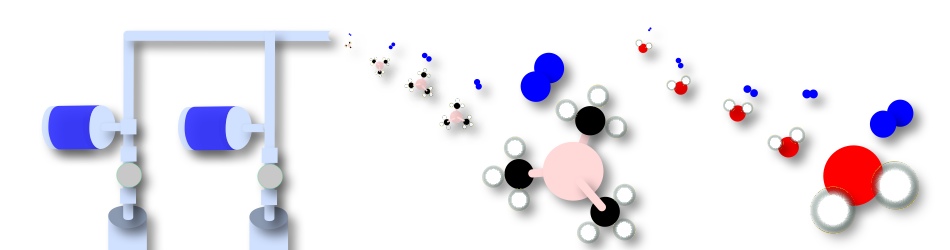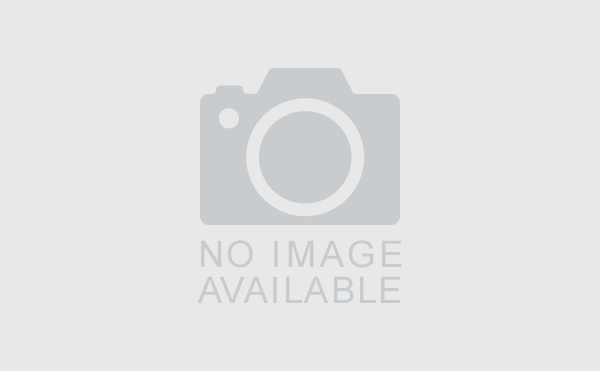ALD/ALE2025について
以下個人的な私見です。
少し古くて恐縮ながら、今年の6月22日から開催されたALD/ALE学会で注目したポイントを3つ挙げてみたいと思います。どちらかというと非半導体のセッションばかり聴講しておりましたが、今回は半導体関連ばかりが目につく年でした。
① メタルMo: DRAM製造で世界1位に上り詰めたSK HynixがNAND Flashメモリーにメタルモリブデン(Mo)を採用することを認めていました。(モリブデンは既に装置メーカーLAM Research社と材料メーカーのJX金属の子会社東邦チタニウム社の 発表よりもその大量生産での採用は間違いないと思われます。LAM Reseach社の説明にもある通り、密着層やバリア層が不要なためプロセスの簡略化とコストダウンに効くことになりそうです。材料の変更は多大な研究と検証が必要なため、本当によくやられたと思います。)
② 酸化物半導体:、昨年のALD/ALE2024で東京大学の小林正治先生が招待講演でこの酸化物半導体を採用した複雑なデバイス構造を発表されており、とても感銘を受けました。今年も引き続き、GAA (Gate All Around)の内側にある半導体材料IGZOやInGaOxの発表が非常に増えておりました。
③ MLD = Molecular Layer Deposition 分子層堆積技術というALDの亜流と思われていたこのMLD(あるいはALD/MLDの混合技術)の発表が増えておりました。(日本では一般的には語られておりませんが、MLDで形成した有機膜などを次世代のEUVレジストで使えないかの検証がALD界隈では研究されております。現在のフォトレジストはスピンコータで300mmウエハーに塗布成膜してますが、ウエハーの中心部と端で厚みが大きく異なるため条件出しが難しくなります。ただでさえプロセスマージンが狭いのにです。もしMLDでレジストが作れるならば、レジストは極めて均一に成膜されるため、プロセスマージンを大幅に緩和できると考えられます。加えて、MLDは下地の原子配列に沿うように成長するため、レジストのラインエッジラフネスが大きく改善するとの報告もあり期待が大きいのです。弱点としては、コストの増大と実績のなさでしょうか。)